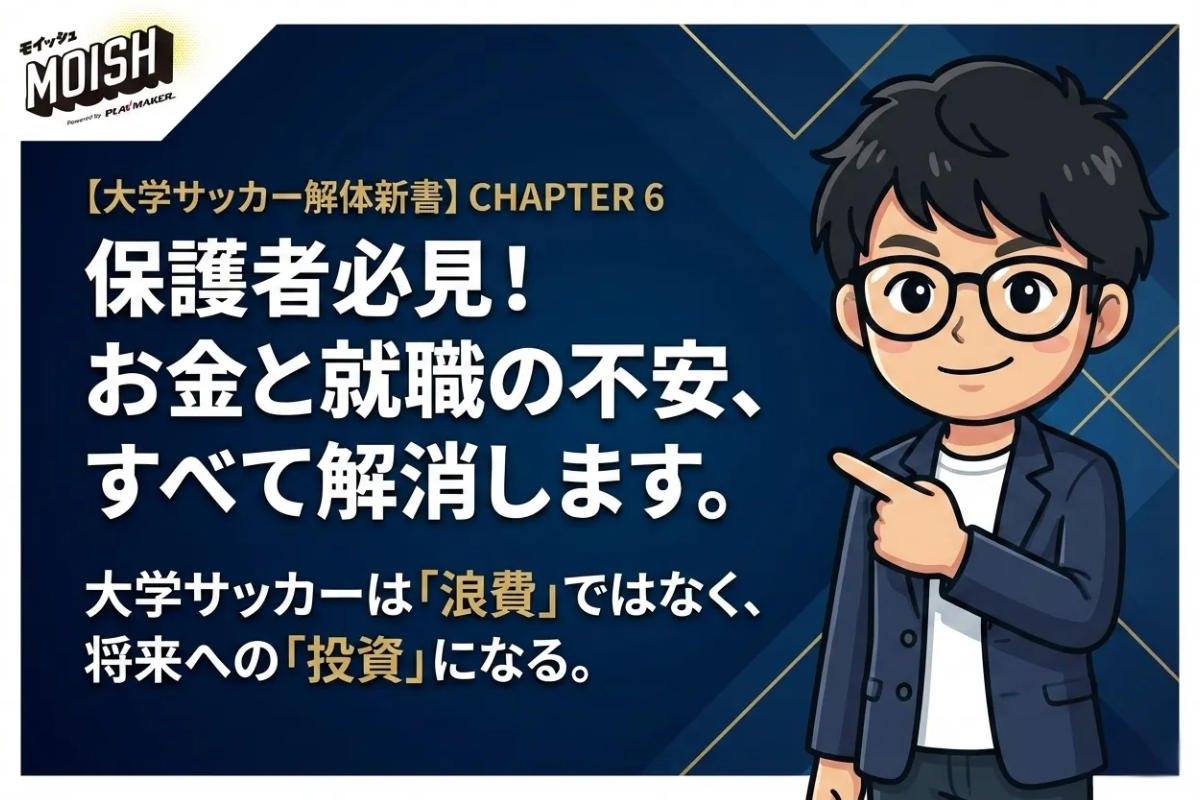大学サッカーの4年間は、
高校とは比べものにならないほど“濃い”。
大学サッカーの構造(Iリーグ・リーグ戦・学生主体運営)を組み合わせると、1日の生活は想像以上にタフで、想像以上に楽しい。
ここでは、全国の大学サッカー部を支援してきた視点から強豪校の“リアルな1日” を描き出す。
INDEX
1. 朝:朝から勝負が始まる
強豪校で朝練の場合、朝からスケジュールがパンパンだ。
05:00 ー 起床
寮生活の大学では、ほとんどがこのくらいに起きる。
06:00 ー 朝練(※朝練のチームも多い)
ウォーミングアップの時点で高校時代の強度を超える。
判断の速さ、フィジカル、球際、全てが違う。
大学サッカーでは “やらされる練習” は存在しない。
4年間で成長する選手は、自らの意思でレベルアップを図る。
ここで“今日の自分の調子”が決まる。
朝練前は補食程度で済ませる場合、練習後に寮であれば食堂で、一人暮らしであれば持参した朝食などでエネルギー補給を行う。
09:00 ー 授業へ
授業の間に移動・復習・グループワーク。
体育会だから授業が免除される…なんてことはない。
2. 昼:授業、授業、授業
大学は高校と違い、
・自分で時間割を作る
・空きコマがある
・グループワークが多い
この自由度の高さは強みであり、弱みでもある。
総合大学では文系・理系・教職・ITなど多様な学生に囲まれる。
サッカー部以外の仲間と出会い、価値観が一気に広がる。
学年が上がるにつれ、授業は減り、自由な時間が増えるということは自分自身がどうその時間を使うかで成長度が決まる。
3. 夕方:自分の時間が始まる
16:00〜19:00 ー 自主練習・チーム運営・授業の課題
ここが大学サッカー最大の“伸びしろ”の時間
・トレーニング施設で筋トレを行う者
・グラウンドで自主練をする者
・チーム運営のために力を注ぐ者
・授業の課題をこなす者
・アルバイトをする者(認められていれば)
・息抜きをするもの
計画的に時間を使い、自身を高める経験は、社会に出て“超強力な武器”になる。
4. 土日:毎週が戦い
大学サッカーは週末が試合だ。
・Aチームリーグ戦
・練習試合
・Iリーグ(B・Cチーム)
・その他試合
大学サッカーは誰にでも試合チャンスがある世界。
高校より出場機会が多い選手は山ほどいる。
自分と向き合い、Aチーム昇格やスタメンを目指して戦う
5. 大学によってさまざまな活動パターンが
ここまで紹介してきたのは、強豪校の朝練パターン。
これ以外にも夕方に活動をしているチームも多い。
大学1年生は授業が比較的多いものの、学年が上がるにつれ、授業数は減り、より自由な時間が増えてくる。
自己研鑽に励む、たくさんの思い出を創る、友達と過ごす。
サッカーを続けながらでも、自分のやりたいことは思いっきりできるはずだ。
6. 大学サッカーは“自立と挑戦”の4年間
1日の生活を見ただけでもわかるように、
大学サッカーは“自由”であり“責任”であり“挑戦”だ。
高校のように
「決められた時間に行けばいい」
世界ではない。
自分で選び、自分で動き、自分で戦う。
この4年間をやり切った大学サッカー選手が、
就職でも、社会でも、人生でも強くなる理由はここにある。